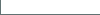 先日、先輩が死んだ。先輩とは名前を呼び合うほど親密な関係ではなかったけれど顔を合わせれば挨拶をする程度のかかわりはあった。 強いて言えば彼の古くからの馴染みである少女が僕の同級生だというだけで、朝から涙で頬をぬらす彼女を必死に慰める僕はどうすれば彼女が泣き止んでくれるのだろうということだけで、ちっとも亡くなった先輩に関しての感情なんて持ち合わせていなかった。 ラビが死んだのはわたしのせいなのよ、と彼女。 僕から言わせて貰えば何を思ってそれを言ったのだろう。詳しい話を聞いたところによると、どうやら学校が終わってから喫茶店に行こうと約束をしていて、そして先輩が遅刻したらしい。 電話向こうで謝る彼に彼女は遅いのよ、待ちくたびれたわ早くして、そう言って電話を切ったらしい。恐らく急いだ彼は信号待ちの途中に飛び出したのだろう、交通事故であっさり死んでしまった。 それがどうして彼女――リナリーのせいだというのだろう。 私が急かさなければよかったのよ、だから私が殺したも同然だわ。そう言って彼女はさめざめと泣くのだけれど、別に彼女がナイフを持って彼を刺したわけでもないし。(もしそうであれば僕は胸を張ってそうですね君が殺しましたね、と優しく言うだろう) 先輩の葬儀は平日ということもあってかひっそりと簡素にしめやかに行われた。それでも人徳かはたまた社交辞令か、同級生らしき人々が大量に葬儀に顔を覗かせたのだけれど。 リナリーに一緒に葬式に出ようといわれた僕は頷いたはいいものの、どうすればいいのかわからなくて制服に身を包まれたままぽつねんと立っている。白と黒のコントラストで目がどうにかなってしまいそうだ。 飾られた先輩の顔写真は見ているこっちが笑ってしまうほどの穏やかな笑顔で、その笑顔を見る限り先輩は優しい人だったんだなあ、と思う。 棺を覗き込んで泣いているのは恋人か、リナリーほどではないけれど綺麗な顔をした女の人が泣きながら先輩の名前を呼んでいた。 愛されていたんだなぁ、と思いつつ、さりげなくポケットの中の携帯を確認する。メールはきていないようだ。 「アレンくん」 涙声のままリナリーが歩いてきた。 反射的に携帯をポケットの奥に仕舞いこんで、薄く笑顔を浮かべて返事をする。リナリーは僕の隣に座り込むと、誘っておきながら放っておいてごめんね、と言った。 別に授業が潰れたからいいんだけどな、と心の中で思っておきながら、気にしないでよ、と口にする。 僕は最低の人間だ。 |