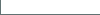 「…落ち着いた?」 小さな声で問いかけると、うん、と彼女は頷いた。 僕の服の裾をきゅうっと掴んで、妙に力を入れるものだから、中途半端に皺がついてしばらくは取れそうに無かった。 よしよしと子供をなだめるように頭を撫でるのだけど、きっと彼女にとって今僕がしていることなどちっとも意味のないことなのだろう。 「…ラビは、」 「うん?」 ぽつりと彼女が呟くから、僕は反射のように聞き返した。 涙を浮かべた瞳は悲しそうだけど、僕にはその悲しみはない。対比的な僕の表情に一瞬言うことをためらったのだろうけれど、彼女は続ける。 「……ラビは、いい人だったわ」 「…うん」 心持ち顔を上げた彼女は嘘つき、何も知らないんでしょというような顔をしていたけれど僕は何も言わず視線をそらした。 「アレンくんはラビのことをどう思っていたの?」 「え、」 急に勢いづいた彼女の気迫に押されて、ほんの少しだけ背後に体を傾けた。 後ろに倒れかけたからか、腹筋に力が入る。ふ、と軽い息を吐き出して僕は表情を変えないまま呟いた。 「……人当たりのいい、先輩だと思ってたよ?」 「……………………」 たっぷりの沈黙の後、ごめんね、と言って彼女は立ち上がる。 再び浮かび上がって来たのだろう、涙を隠しながらまた葬列に紛れ込んだようだった。そうでなくとも制服とは違う、正規の喪服に身を包んだ黒髪の彼女はこの景色になじみやすいというのに。 ただ、ひとつ気になる。どうして彼女は僕を見て、背中を向けたその瞬間、ラビが浮かばれないわ。そう言ったのだろう。 残念ながら僕は無宗教だ。 葬式で何か唱えろだとかそういったことを言われた気がしたが、何も唱えなかった。 死者の冒涜云々を考えたけれど、さらに考えてみれば死んだ人間に僕はほぼ関係ないわけで、だから唱える義理も何も無い。 曲がりなりにも先輩であって、名前も覚えてもらっていたのだから安らかに眠って欲しいとは思うけれど、だからといってそこまで自分の労力を消費したくはない。 自宅のドアの鍵穴に鍵を差し込んで、右に回す。 小さな音がして、そのまま引っ張るとドアが開いた。履いているローファーがカツカツと音を立てる。 コンクリートのように硬い床を少しだけ蹴りつけて、靴を脱いだ。フローリングの床に足をつけると、靴下ごしでもひんやりと冷たい。 「おかえりぃ」 「ただいま…………」 リビングのドアを開けてソファの上に鞄を置いた。 テレビをつけ、自身もソファに寝転がる。時間は丁度7時。突然な芸人の笑い声からはじまるお笑い番組の音声が部屋に響く。 「……………?」 待て。 待て僕。今僕は誰と話した? 確か家には鍵がかかっていたはずだ。そもそも、親は自我が生まれる前に亡くなったか蒸発かでいないし、育ててくれた義父も数年前に他界した。 プラス、そこからさらに育ててくれた義父(と呼びたくないので今は師匠と呼んでいる)も音沙汰なしで、ついでにおかえりなんて言うような優しい人間ではないし、むしろもう人間と思いたくない。 「ッ誰!?」 立ち上がり、咄嗟に携帯を持ち、警察の番号を打ち込む。通話ボタンを押すだけでいつでも通報が出来る体制にしてから、壁に背を預けた。 どこから来ても真正面から戦えるように。 「や、あのさ、警戒しないでほしいんだけど」 「…どこにいる!!?」 声は確かにこの部屋の中から聞こえる。もしやソファの下にでも隠れているんだろうか。半ば焦り、本格的に通報しようと通話ボタンに人差し指を押し付けたその瞬間、タンマ!という声と共に背後から伸びてきた手に手首を掴まれた。 背 後 か ら 伸 び て き た 手 に 掴まれた。 するりと壁から抜け出てきた、今日の昼顔を合わせたばかりのあの見た人も一緒に笑ってしまいそうな笑顔がそこにある。 ごめん驚かせるつもりはなかったんだけどさ、そう言ってからからと笑った彼を目の前にした僕は持っていた携帯を落としてしまった。 きゃーとかいう悲鳴初めて上げた。 |