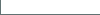 これは何かの罰ゲームでしょうか。 それとも、あれですか。葬式で何もしなかった、安らかに眠ってくださいとお祈りさえしなかった僕への試練でしょうか。 けれど罰ゲームにしては性質が悪すぎるし、試練にしては目の前の彼が穏やかな顔をしすぎている。 くすくすと喉の奥で笑う彼に対して、僕は引きつった表情のまま一歩二歩と後ずさった。追いかけるように少しずつ近寄ってくる彼の体は微妙に、いやかなり、透けている。 「や、そーやって逃げる気持ちよくわかるさー。俺だってこんな目に遭ったらぜってぇ逃げるもん」 ならばもう少し思いやりというものをもって僕から離れてくれないだろうか。 師匠から教わったカンフーだとか空手だとかの闘技が頭の中から綺麗さっぱり取り除かれていく。人間相手ならお手の物でも、体の透けた未確認物体を前にしては何も出来ない。 「……なんで、……?」 自分でも驚くほど、出した声は枯れていた。彼はふうわりと天井に浮かび上がったかと思えば(どうやら自分なりに距離をとったつもりらしい)、至極遠慮したように微笑む。 「俺もわかんないんだけど、気づいたらここにいて、それが偶然にもウォーカーん家だったんさぁ」 こう見えて俺も結構テンパってるんさー、と、彼は再び天井をぐるぐる回る。つられるように僕の目もその動きを追うけれど、明らかに人間の動きとは思えない。そもそも物理学的な問題から言わせてもらうと人間は透けたりしない。 つまりは、ここにいる物体は「人間」ではないということ。 理解するまでどれだけの時間を消費したのだろう。頭の中でどこか自分は関係ないと割り切る自分がいる。今直ぐにリナリーに連絡を取るべきかとも考えたけれど、今日の彼女の様子からしていきなりこんなことを告げれば、こんなときに冗談なんかやめて、と一蹴されるのがオチだろうという結果に落ち着いた。 突然冷静になった頭が、ひとまず休めと自分自身に命令する。すとんとその場にしゃがみこんで、本当に彼が「彼」なのかを確認した。 「先輩、……ですよね?」 「ん。ラビっす」 僕が落ち着いたんだと理解したらしく、またふうわりと近づいてくる。「…近づいてもダイジョブ?」まるで怒られるのを前提としているような、少しびくびくした聞き方に苦笑さえ漏れてしまった。 頷けば、安心したように“地面に足をつけた”ようだ。じっくり見ればかすかに床より浮いているのがわかる。けれど本人にしてみればそれが足をつけたということで。 見上げて、まじまじと見つめても、やはりそれはラビ先輩だった。適度な長さの赤毛に、眼帯で隠した右目、白い清潔そうなカッター、黒いズボン。どう見てもそれは生前の彼の学生服であり、姿である。 「ははっ、こんなにウォーカーに見られたのはじめてかも」 「そう………、で、す、ね」 先輩が面白そうに呟いたので、僕も不謹慎ながらも微笑んだ。すうっと浮き上がった先輩が、昔人気を集めたスーパーマンのように両手を突き出して天井を飛び回る。見て見てウォーカー、と言いながら、ソファをすり抜け、テレビをすり抜け、ダイニングの壁をすり抜け観葉植物をすり抜け…、と、これもまた不謹慎ながら楽しんでいるようだ。 「…先輩、とりあえず止まってください」 このままでは話が始まらない、ととめてみれば、わざとらしく急ブレーキを踏んで先輩が止まる。先輩をすり抜けて向こうのテレビが見えるという事実が、激しく僕に頭痛を齎した。 「まずは、これからどうするか考えましょう?」 「これから、って?」 「このまま僕の家にいたところで何かが解決するわけでも無いでしょう。例えば、家に戻るとか……」 僕の提案に、先輩は目を軽く瞬かせ、何事かを理解したかと思うとさわやかに笑って首を横に振る。だめだめ、と言いながら手を左右に揺らした。 「それ、無理。俺、ウォーカー以外には見えないみたいなんさ。お前が帰ってくる前に隣の部屋とか行ってみたけど、反応なし」 「………え」 そう言ったかと思うと、話に飽きたのかまた飛び上がってくるくると天井を回り始めた。すうっと上に消えたかと思うと(恐らく上の階の部屋に向かったのだろう)、1分も経たないうちに戻ってきて、「やっぱ駄目だったー」と明るい声で報告する。そんな、まさか。どうして、僕にしか。いや、僕だから、なのか?――ふいに、頭の中にリナリーの声がよみがえる。『ラビが浮かばれないわ』――、もしや、僕がお経を唱えなかったからだろうか?心から悲しまなかったからだろうか?(頭痛がする)ベランダに出て意気揚々と浮かび、空中ドライブを楽しんでいる先輩を横目に、僕は必死にその場に崩れないように体に力を入れた。 |